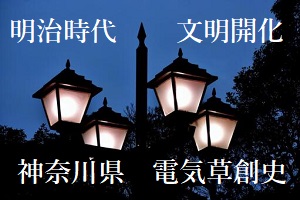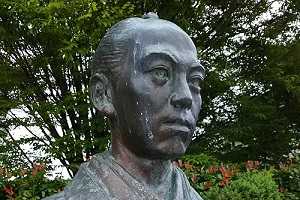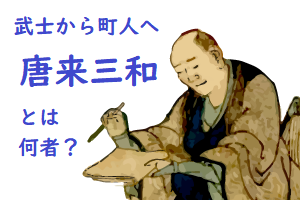時は安永5年(1776年)、平賀源内がエレキテル(elektriciteit、ゐれきせゑりていと)を修理復元。大いに世の耳目を騒がせました。
聞けば源内先生、電気の概念はよく知らなかったそうです。そんな中でエレキテルを修理したのですから、その才知は大変なものでしょう。
しかし静電気がパチッと出るだけではどうにもならず、実用性は得られないまま歴史の片隅に埋もれてしまいました。
それから1世紀あまり。明治23年(1890年)10月、神奈川県にも初めて「電気」がやって来たのです。
神奈川県横浜市中区常盤町に、そのことを示す「神奈川県電気発祥の地」と刻まれた石碑が佇んでいます。
今回は神奈川県における電気の草創史を紹介しましょう。
神奈川県の電気草創史

明治23年10月(1890年)横濱共同電燈會社が、この地に火力発電所を建設し、神奈川県で初めての電力供給を開始いたしました。
当時の発電所は出力100キロワットの石炭火力で、お客さまは約700軒でした。
※「神奈川県電気発祥の地」碑文より。
碑文の左にはエジソン式直流発電機のエッチング図が示され、力強く発電した往時を偲ばせます。
その発電機で100キロワット(kw)の電力を供給したそうですが、これはどのくらいの電力なのか、ちょっとピンと来ませんね。
一説によると、現代人の一人暮らし世帯が1時間に消費する電力量がおよそ200kwh(キロワットアワー。1時間あたり電力量)。
発電機の100キロワットがkwhだったと仮定して、現代では一人暮らし世帯が使う電力量の30分程度しか賄えないことになります。

ちなみに4人世帯だと月に約300~400kwhとのこと。つまり15~20分程度しか賄えません。
それだけの電力を700灯(1世帯およそ1灯)で分け合っていたと考えると、現代からは想像できないほど暗い生活環境だったことがうかがわれます。
それが30年後の大正9年(1920年)には横浜市内の約48万軒にまで需要が拡大しました。
創業当初からおよそ685倍という拡大ぶりは目を見張るもので、翌大正10年(1921年)には東京電燈(現代の東京電力)と合併しました。
それから関東大震災(大正12・1923年)や横浜大空襲(昭和20・1945年)などをくぐり抜け、令和の現代では東京電力の関内変電所となっています。
終わりに

今回は神奈川県に電気がもたらされてから、百数十年の歴史をごく駆け足でたどってきました。
平賀源内がエレキテルの火花で人々を驚かせてから百数十年で街の夜闇を照らし、それから百数十年で、様々なものを動かすまでになったのです。
今や生活になくてはならない電気。神奈川県においては、ここ横浜の地からすべてが始まったのでした。
初めて暗闇に灯った電気の光を、遠く昔の源内先生が見ていたら……そう思うと、先人たちに対する感謝の念も一入ですね。
「神奈川県電気発祥の地」記念碑
- 〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町1丁目6
- JR根岸線「関内駅」から徒歩2分