※前回の物語はこちら。
明治時代初の国際結婚「EUの母」と呼ばれた「黒い瞳の貴婦人」クーデンホーフ光子の生涯【上】
明治時代、オーストリア=ハンガリー帝国の貴族ハインリヒ・クーデンホーフと結婚し、日本からヨーロッパへと旅立った青山みつ改めクーデンホーフ光子(-みつこ)。
周囲の偏見や差別感情に晒されながらも、夫の愛情を頼りに耐え抜き、努力の末に知性と教養を身に着けて「黒い瞳の貴婦人」「レディ・ミツコ」などと呼ばれ、一目置かれるようになった光子。

社交界の華として夫を支え、活躍した彼女ですが、その前途には暗雲が立ち込めていたのでした……。
夫の急死、遺産争い、第一次世界大戦……相次ぐ試練の日々
すっかりヨーロッパ社交界にもなじんできた光子でしたが、人生の転機は突然やってきます。
明治39年(1906年)5月14日、夫ハインリヒが心臓発作を起こして急死してしまったのです。
予てより遺産はすべて光子に相続させるように遺言していたのですが、ここへ来て親族たちは「アジア女なんかに、クーデンホーフ家の財産をくれてやるなどもってのほか!遺言など反故だ!」とばかり訴訟を起こしました。
できれば穏便に済ませたいけど、ここで引き下がってしまったら、自分はともかく7人の子供たちはどうなってしまうのか……。
「えぇ、受けて立とうじゃありませんか!」
長男ハンス、次男リヒャルト、三男ゲオルフ、長女エリザベート、次女オルガ、三女イーダ、末っ子(四男)のカルル……この子たちを守るためなら、たとえ世界を敵に回しても闘ってみせる……光子は法律知識を猛勉強して訴訟を闘い抜き、ついに勝訴を勝ち取ったのです。

「これからも、この財産を狙ってくる輩がいるはず……騙されないように、資産運用・管理の知識も身につけなくては……」
クーデンホーフ家と距離を置くためか、教育に適した土地としてウィーンへ移住した一家8人は、そのまま静かに暮らそうと……したのですが、時代はそれを許しませんでした。
「日本人は敵だ!」「黄色い日本女が、貴婦人の猿真似をするな!」
大正3年(1914年)に第一次世界大戦が勃発すると、オーストリア=ハンガリー帝国は光子の祖国である日本と敵対。日本出身の光子に対する差別感情が高まります。
「……母さん。僕たち、戦争に行ってくるよ」
日本の血が混じっているとイジメられでもしたのか、長男のハンスと三男のゲオルフは愛国者であることをアピールするため兵役に志願し、出征していきました(ちなみに、次男のリヒャルトは肺病のため兵役免除)。

「あぁ、誇り高きクーデンホーフ家の子息が兵役なんて……」
とは言え、光子も息子たちとの別れを嘆き悲しんでばかりもいられず、自身も赤十字を通じて資金や食糧を供出、まさに「欲しがりません、勝つまでは」の精神で苦難の時期を耐え忍びます。
けっきょく戦争には負け、オーストリア=ハンガリー帝国は崩壊してしまったものの、息子二人が生きて帰って来てくれたことが、せめてもの救いと言えるでしょう。
「これでまた、みんなが揃った……家族の絆さえあれば、人生いくらでも建て直せる……」
気を取り直そうとした光子を、又しても新たなトラブルが降りかかります。
親の心子知らず……次男リヒャルトの駆け落ち婚
「……断じて認められません!」
時は大正7年(1918年)、終戦から間もなく次男のリヒャルトが人気女優のイダ・ローラントと結婚すると言い出しました。
「母さんが反対ならそれでもいい。僕は僕の人生を生きるだけだ!」
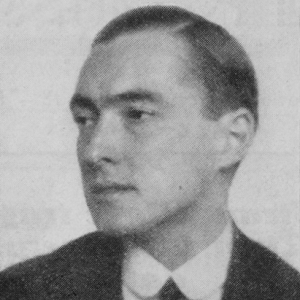
リヒャルトの意志は固く、光子がどれだけ止めても聞く耳を持ちません。
光子が反対した理由は、イダが(1)ユダヤ人であること、(2)2回も離婚しているバツ2≒性格に難がある可能性が高いこと、(3)女優という卑しい職業についていること、そして(4)リヒャルトと10歳以上の年齢差があり、出産を望めないであろうこと……などがあります。
(※)これらの差別的価値観は、あくまで当時のものであり、現代的の価値観と相容れないことは言うまでもありません。
「誇り高きクーデンホーフ伯爵家の子息が、そんな女を伴侶とするなど……恥ずかしいとは思わないのですか!」
亡き夫ハインリヒからクーデンホーフ家の名誉を受け継ぎ、それを必死に守るために血を吐くような努力をしてきたというのに、たとえ我が子であろうと、それをいとも容易く否定するような結婚を、認める訳には行きませんでした。
「いいや、母さんは間違っている!ユダヤ人であろうがオーストリア人であろうが、努力によって成功を勝ち取り、誇り高く生きている人間はいくらでもいる……まさに日本人である母さんがそうじゃないか!」

「2回も離婚しているのは、夫の方がろくでもなかった可能性もあるだろう……詳しい事情を知りもしないで、ただ離婚歴だけを見て彼女だけを責めるのは、公平を欠いていると言わざるを得ない!」
「女優は卑しい職業と言うが、世の中に求められるから存続しているいかなる職業にも貴賤はないはず……それでも卑しいと言うなら、人々が汗水たらして働いた収穫や利益の中から税金を吸い上げ、かすめ取る政府や貴族、資本家たちは、もっと卑しい寄生虫じゃないか!」
「子供?そんなもの、いくら若くっても伴侶との相性で産めない事例はいくらでもあるし、女性だけの責任と決めつけるのは、医学的にも間違っている!そんなに子供が欲しいなら、妻に産ませなくたって、養子をとれば十分だ!」
……議論は平行線をたどるばかり、頑として主張を譲らないリヒャルトは、結局イダ・ローラントと駆け落ち。この結婚をどうしても認められない光子は、仕方なくリヒャルトを勘当し、死ぬまで再会することはありませんでした。
その後、リヒャルトはイダ・ローラントの経済的支援によって、ヨーロッパの統合を主張する著書『汎ヨーロッパ主義』を出版。

この思想が世に受け入れられて成功を収め、後にEU(欧州連合)の基本構想となったことから、現代では「EUの父」と呼ばれるのですが、それはまた別のお話し(余談ながら、リヒャルトはイダと離婚、その後2回再婚しています)。
「母さんは時代遅れだよ!もう世界は変わりつつあるんだ!」
ちなみに、長男のハンスもユダヤ人のリリー・シュタインシュタイナー(オーストリア=ハンガリー帝国空軍の女性パイロット)と結婚、後に女優のウルスラ・グロースと再婚しますが、ここでも光子は大反対したことでしょう。
「私がこれほどまでにクーデンホーフ伯爵家を守ろうとしてきたのに、どうしてみんな解ってくれないの……?」
亡き夫から受け継いだ家と遺産を守るため、誰よりもクーデンホーフ伯爵家にふさわしくあろうとした光子の厳格さは、変わりつつあった次世代の子供たちから否定され、孤独な晩年の引き金となってしまうのでした。
※参考文献:
- 木村毅『クーデンホーフ光子伝』鹿島出版会、1986年10月
- シュミット村木眞寿美 編『クーデンホーフ光子の手記』河出書房新社、2010年8月
- 堀江宏樹ら『乙女の日本史』東京書籍、2009年7月
- 南川三治郎『クーデンホーフ光子 黒い瞳の伯爵夫人』河出書房新社、1997年5月



コメント