「おのれ、一服盛りおったな!」
武力を用いることなく敵を倒す一策として、古代から近現代にいたるまでしばしば用いられてきた毒殺。

現代のサスペンスだと、よく青酸カリとか鳥兜(トリカブト)などが使われるようですが、昔の人はどんな毒を用意したのでしょうか。
史料や文献を調べてみると、しばしば鴆(ちん)毒なるものが登場。軽い響きがかえって薄気味悪い印象……いったいこれは何なのか、今回はそれを紹介したいと思います。
伝説の毒鳥は実在した?
まず、鴆とは古代中国の文献に登場する毒鳥で、図鑑『三才図絵(さんさいずえ。明の万暦35・1607年)』によれば紫黒色の羽毛と赤いクチバシをもって目は黒く、首の長さは7~8寸(約21~24センチ)。

いつも毒蛇ばかり食べているせいで体内には猛毒が蓄積されており、あまりに毒が強いため、畑の上を飛んだら作物がすべて枯れてしまったとか、糞をかけると岩が砕けたなんて記録があります。
そんな鴆の毒は無味無臭かつ水に溶ける性質があるため、羽毛を一枚とって酒に浸すと、相手に気づかれることなく毒殺できたとか。
あまりの猛毒なので政府当局もしばしばこれを規制し、鴆の生息地であった長江より北に持ち込んではならなかったとか、鴆を発見した場合は駆除するために山を丸ごと燃やしたとか、ヒナを都に持ち込んだ者をヒナもろとも処刑したなど、相当神経を尖らせていたようです。
しかし、それまで毒を持つ鳥類が確認されていなかった事から、鴆は伝説上の生き物(あるいは何かの寓意)であろうと忘れ去られていきます。
しかし、平成4年(1992年)になって東南アジアのパプアニューギニアでピトフーイという毒鳥が発見され、他にも同地域で複数の毒鳥が発見されたことから、これら(あるいは既に絶滅した種族)が鴆のモデルになった可能性も否定できません。

……が、現実的には無機化合物の一種である亜ヒ酸(あひさん。H3AsO3)と考えられており、その製造法については古代中国の書物『周礼(しゅらい)』に記述があります。
五毒(雄黄ゆうおう、礜石よせき、石膽せきたん、丹砂たんしゃ、慈石じしゃく)を素焼きの壺に入れて三日三晩焼いて出て来た白煙で鶏の羽毛を燻(いぶ)して完成、これを酒に浸したものが鴆酒(ちんしゅ)です。
煙で羽毛を燻すのは、気化した毒成分を細かな羽毛にくっつけて結晶化させるためと言われ、日本でも三酸化二ヒ素(As2O3)を同様の方法で作っています。
毒殺の犠牲となった英雄たち
さて、そんな鴆毒はじめ、戦国時代にはどれくらい毒殺が横行したのでしょうか。未然に防がれたり、病死など別の可能性もあったり諸説あるものも含め、見ていきましょう。
※/の右側は犯人もしくは関与が疑われる者。
足利義植(あしかが よしたね。第10代将軍)/日野富子(ひの とみこ。伯母)
足利義栄(あしかが よしひで。第14代将軍)/松永久秀(まつなが ひさひで。家臣)
甲斐宗運(かい そううん。阿蘇氏家臣)/孫娘(実名不詳。木山紹宅室)
加藤清正(かとう きよまさ。大名)/徳川家康(とくがわ いえやす。政敵)
蒲生氏郷(がもう うじさと。大名)/伊達政宗(だて まさむね。政敵)
長倉義興(ながくら よしおき。佐竹氏家臣)/佐竹義宣(さたけ よしのぶ。主君)
那須高資(なす たかすけ。大名)/千本資俊(せんぼん すけとし。家臣)
蜂須賀重鎮(はちすか しげちか。蜂須賀至鎮の誤記か)/氏姫(うじひめ。側室?)
政敵同士はいざ知らず、主君と家臣が殺し合い、親族同士も殺し合い、果ては夫婦や祖父と孫まで……まさに戦国乱世、骨肉の争いが演じられたのがよく分かります。

ここにある以外にも、記録に残らない毒殺事件が無数に起こっていたことでしょう。軍記物語『土佐物語』にも、鴆毒を井戸に放り込んだところ、飲んだ兵士たちが相次いで気絶したなど、いざ有事には無差別テロも横行したようです。
ちなみに、鴆毒以外の毒としては砒素(ヒソ)や附子(ブス。鳥兜)などが用いられ、当時の医学ではどの毒かを見分けることは出来ず、主に「毒殺か、あるいは病死か」のみ判別されたと言います。
(現実に死んでいることに違いはない以上、今さら何の毒かを見分けるよりも、まず誰が盛ったかを突き止め、処罰する方が優先でしょう)
まとめ・鴆毒とは何か?
一、伝説の毒鳥・鴆の羽毛とされているが、実際には砒素系の毒物説が有力
一、近年発見された東南アジアの毒鳥(もしくは絶滅した仲間)がモデルの可能性も
以上、数多くの英雄たちを葬り去った鴆毒について調べ、紹介してきました。

直接攻撃を加えて「自分の手を汚す」ことなく、また発覚や返り討ちのリスクを低く抑えながら相手を死に至らしめる毒殺ですが、手段の陰惨さ・卑劣さから、加害者の心理的負担は、より大きかったのではないでしょうか。
そもそも殺し合いなんてないに越したことはないものの、どうしても命のやりとりをせねばならない状況であれば、せめて堂々と誇り高くありたいものですね。
※参考文献:
- 岡村青『「毒殺」で読む日本史』現代書館、2005年8月
- 杉山二郎ら『毒の文化史』学生社、1990年3月
- 立木鷹志『毒薬の博物誌』青弓社、1996年1月



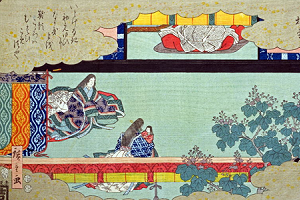
コメント