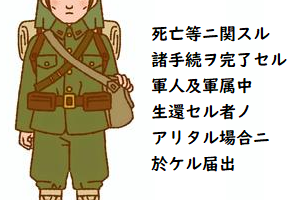平仮名の「そ」って、2通りの書き方をしますよね。
1つめの書き方は、一筆書きで「そ」。2つめの書き方は、1画目を離してこのようになります。

これはどっちが正しいのでしょうか?そもそもなぜ2通りの書き方があるのでしょうか?
という訳で、今回は平仮名の「そ」について調べてみました。
※以下、一筆書きの書き方を「Z型」、2画の書き方を「ソ型」と呼びます。上半分がそう見えるからです。
平仮名「そ」の成り立ち
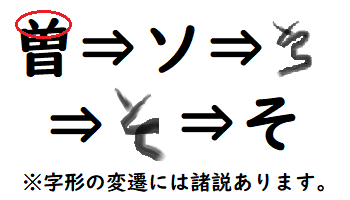
まずは平仮名の「そ」が、どのように成り立ったのかを見ていきましょう。
実はZ型もソ型も、両方とも漢字の「曽(そ、そう)」から成り立っています。
まずは最上部の冠を切り取って、片仮名の「ソ」が成り立ちました。
続いて平仮名の「そ」は、片仮名の「ソ」に中下段をシャシャッと加えたようです(曽の草書体)。
これがソ型の始まりと言えます。
やがて「いちいち画数を分けるのがめんどくさい」と思ったのか、あるいは筆の勢いによって一筆書きのZ型となりました。
※そもそも別の字体を作ろうなどとは考えていなかった(たまたま一筆書きになったのが定着した)可能性も考えられます。
このような由来を考えると、歴史的にはソ型の方が古いと言えるでしょう。
ただし実務的にはどっちが古いか、よりも、どっちが正しい(適切)かが重要となります。
【結論】どっちも正しい

果たして平仮名の「そ」はZ型とソ型のどっちが正しいのでしょうか?
結論から言うと、決まっていません。
例えば漢字なら、常用漢字のように一定の基準が設けられています。
しかし平仮名や片仮名については、こうした基準が設けられていません。
そのため、Z型とソ型どっちの「そ」も正しい(少なくとも間違いではない)ということになります。
ちなみに学校などの教育現場においては、教えやすさ&覚えやすさの都合からどっちかに統一(指導)することが多いようです。
そうなると、やはり一筆書きできるZ型の方が、より有利と言えるでしょう。
とは言え、それはあくまで現場の都合。指導者によってはソ型を用い、指導するケースも考えられます。
Z型とソ型、どっちの「そ」にしても強制力はなく、ケースバイケースで使い分ければいいでしょう。
※ただし教育を受けている立場の場合、ある程度は相手に合わせてあげるのも一策かも知れませんね。
オマケ
「そ」の書き方について、こんなポスト(X投稿)を見つけたので、紹介します。筆者の個人的にお気に入りです。
ざつねこ
@zasshu_nekoなんかふと思い出したんだけど
僕はひらがなの「そ」は右のように書くんだけど、小学1年生の時に学校の先生から「それは”うそ字”よ!」とこっぴどく叱られて左に直すように言われた
でも僕は「うそまで言うか 頭にきた 絶対直さねー」って右のままで押し通したってくらい幼い頃から強情です
午前8:45 · 2025年7月17日·4.9万件の表示
悪いことをした訳でもないのに、頭ごなしに叱られたことに反発して「絶対直さねー」と決意する偏屈さが最高ですね。
筆者もそういうところが多分にあるので、大いに共感します。
※さっき「教わっている時は空気を読むのも一策」などと言いましたが、不当に責められれば、そりゃ反抗するのも無理はありません。
まったく何ですか「うそ字」って。ろくすっぽ根拠もなく、当局の都合を絶対正義みたいに押しつけんじゃないよ……って思いませんか?
※いや、素直な方が世渡りには好都合なのですが……いやいや、やっぱり押しつけられるのは嫌ですね。
教えるにしても、教わりやすいよう、ある程度は配慮があって然るべきでしょう(※筆者の少年時代も、やはり高圧的な教師が多くいました)。
平仮名の「そ」まとめ
- Z型とソ型の2通りが存在する
- どっちも漢字の「曽」に由来する
- まずソ型が生まれ、筆勢でZ型に変化
- 平仮名については使用の基準がない
- そのため、実務的にはどっちも正しい
- 教わっている時は空気を読むのも一策
今回は平仮名の「そ」について、2通りの書き方を紹介してきました。
キーボードで入力すると「そ(Z型)」のみですが、手書きだとソ型も書き分けられます。
手紙や書道などでは、筆圧や筆運びなどに個性が出せて楽しいですね。
皆さんはZ型とソ型、どっちで「そ」を書いていますか?