あら日本恋しや、ゆかしや、見たや、見たや……
【意訳】あぁ、日本が恋しい、懐かしい故郷の風景をもう一度見たい、見たい……
これは日本を遠く離れた美少女が、帰りたくても帰れない思いをつづった手紙「じゃがたら文(ぶみ)」の一節。

後世「これを見て泣かない者は人ではない」とまで言われたこの文章は、どんな状況で書かれたのでしょうか。
今回は江戸時代に国外追放されてしまった悲劇の美少女「じゃがたらお春(以下、お春)」の生涯をたどってみたいと思います。
鎖国政策によって日本から追放
お春は江戸時代初期の寛永2年(1625年)ごろ、イタリア人航海士ニコラス・マリンと貿易商の娘マリアの日伊ハーフとして長崎で誕生しました。
マリアとは洗礼名で、日本名は不詳。姉のお万(まん)と4人家族だったそうです。

幼少時から美少女で、また読み書きが得意で才色兼備と評判の高かったお春ですが、彼女が15歳となった寛永16年(1639年)、一家を悲劇が襲いました。
これまでも発せられてきた鎖国令によって外国船の入港を禁止すると共に、在留している外国人の追放が決定されたのです。
純粋な外国人である父ニコラスはもちろんのこと、ハーフである娘たちも国外追放の対象となってしまいました。
「お母ちゃんだけは日本に残れるけど……」
かと言って、愛する夫や娘たちと離れて、キリスト教への弾圧が厳しくなる日本にひとり残ったところで、幸せな未来が待っているとも思えません。
「……母さんも一緒に行きます。どこへ行っても、家族が一緒ならどんな苦難も乗り越えられます」
「「お母ちゃん!」」

それでお春の一家4人はバタヴィア(ジャカルタ。現:インドネシア首都)へと追放され、二つ名の「じゃがたらお春」と呼ばれるようになったのでした。
この時、オランダの記録ではお春は「ジェロニマ」、姉のお万は「マダレナ」と呼ばれており、キリスト教へ改宗・洗礼を受けていたようです。
遠く異境へ追放され、もう日本へは戻れない……そんなお春の切ない思いがつづられた「じゃがたら文」は、人々の心を打ったのでした。
別にそこまで不幸でもなかった?裕福なお春たち
しかし、追放後のお春がそこまで不幸だったという話はなく、22歳となった正保3年(1646年)にオランダ人と日本人のハーフで東インド会社に勤務していたシモン・シモンセンと結婚。
シモンは東インド会社の要職を歴任したあと独立して貿易商を開業。経営は順調だったようで、奴隷を所有するなど裕福な暮らしをしていたことが、お春の遺言書(遺産の分配方法などが記されている)などから明らかになっています。
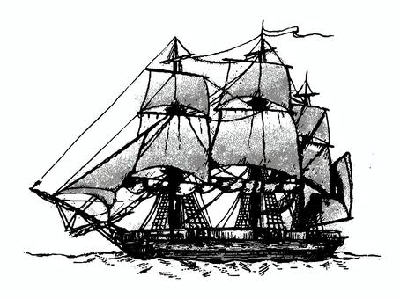
また、お春も7人の子宝(3男4女、又は4男3女)に恵まれて、元禄10年(1697年)に73歳で亡くなるまで、幸せに暮らしたそうです。
いっぽう日本では「悲劇の美少女」「じゃがたらお春」伝説が流行。正徳4年(1714年)に天文学者の西川如見(にしかわ じょけん)が著した見聞記『長崎夜話草(ながさきやわぐさ)』で紹介されて以来、お春人気が高まりました。
しかし、発表直後から物語、特に若き日のお春が書いたとされる「じゃがたら文」の偽作を疑う声があり、古詩を織り交ぜるなど随所に教養のちりばめられた「じゃがたら文」の流麗な文章と、実際にお春が書き残した手紙とのギャップが激しく、今日では後世の創作であろうとする説が有力となっています。
まぁでも、悲劇なんて起こらない方がいいに決まっていますし、お春が嘘をついてカネや同情を集めるなどしたわけでもないのですから、家族みんなが幸せだったのなら、何よりではないでしょうか。
(今日でも架空の伝承を基に地域おこしをしている自治体や団体もありますし、史実と創作の線引きをした上でなら、嘘も方便というものです)
※参考文献:
- 朝日新聞社 編『朝日 日本歴史人物事典』朝日新聞社、1994年10月
- 白石弘子『じゃがたらお春の消息』勉誠出版 2001年7月




コメント