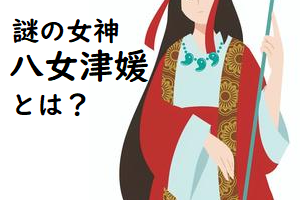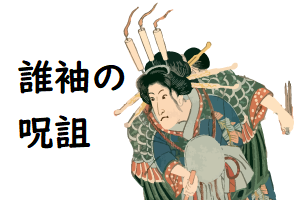日本には八百万の神々がおわし、全国津々浦々に神様の伝承が残されています。
今回はそんな一柱・八女津媛神(ヤメツヒメ。八女津姫神)を紹介。果たしてどのような神様だったのでしょうか。
『日本書紀』の記述より

……丁酉、到八女縣。則越藤山、以南望粟岬、詔之曰「其山峯岫重疊、且美麗之甚。若神有其山乎。」時水沼縣主猨大海奏言「有女神、名曰八女津媛、常居山中。」故八女國之名、由此而起也……
※『日本書紀』巻第七・景行天皇18年(西暦88年)7月7日条
大まかな読み
……丁酉(ひのとのとり)の日、八女県(やめのあがた)へ到る。すなわち藤山を越え、南をもって粟岬(あわのみさき)を望み、詔(の)りて曰く
「その山、峯岫(いわくき)重畳にて、かつ美麗の甚だしき。もしその山に神のありや」と。
時に水沼(みぬま)の県主(あがたぬし)猿大海(さるおおみ)、奏(もう)して言う
「女神(めのかみ)あり、名を曰く八女津媛と、常に山中におわす」と。
故に八女国(やめのくに)の名づけ、これによりて起こるなり……
解説
時は景行天皇18年(西暦88年)。第12代・景行天皇が筑紫(九州)の地を行幸された際、美しい山々を御覧になったそうです。
「山々が幾重にも連なり、実に美しい眺めである。もしかしたら、この地は神が治めていらっしゃるのではないか」
そのお尋ねに対して、道案内を務めていた県主の水沼猿大海(みぬまの さるおおみ)が答えました。
「はい。この地は八女津媛神が治めておいでで、いつも山の中にいらっしゃいます」
彼女の名を讃えて、この地は八女国と呼ばれているのだとか。
その後どうなったのか

……『日本書紀』における八女津媛神の記述は以上となっており、猿大海の説明を聞いた景行天皇が、彼女とどのような関係を持ったかなどは分かっていません。
表敬訪問するなど、友好的な交流を図ったのか?
触らぬ神に祟りなし、と無言で立ち去ったのか?
まさか臣従を要求、あるいは征伐したのか?
一説には佐賀県の吉野ヶ里遺跡あたりを治める女王であったとか、また邪馬台国を統治した卑弥呼のモデルではないかとする説もあるそうです。
八女(やめ)国と邪馬台(やまと、やまたい)国、並べてみると似ていなくもありませんね。
あるいは『日本書紀』で言及された時点で、既に彼女は亡くなっており、神として山中に祀られていた(それで「常に山中におわす」という表現が用いられた)のでしょうか。
彼女の名前は現代でも地名として残っており、福岡県八女市には彼女を祭神として祀る八女津媛神社が鎮座しています。
八女津媛神社は養老3年(719年)に創建され、修験道の行場として栄えました。
境内には彼女が顔を洗ったという石清水「媛しずく(美人の水)」や、子宝祈願に霊験あらたかな「夫婦岩(子だくさんだったとか)」など、ゆかりの史跡が伝わっています。
八女津媛神・基本データ
- 生没:生没年不詳(古墳時代・西暦1世紀ごろ)
- 身分:女神(女王?)
- 領地:八女国(福岡県八女市あたり)
- 人物:美人だった?子だくさんだった?
- 備考:八女津媛神社の御祭神
八女津媛神社データ

- 祭神:八女津媛神
- 神徳:家内安全・健康長寿・美容・子宝など
- 住所:〒834-1401 福岡県八女市矢部村北矢部4015-1
- 創建:養老3年(719年)
- 社格:郷社
- 例祭:11月第3日曜日
- 神事:浮立(ふりゅう。5年に1度、例祭と同日)
- 史跡:媛しずく、夫婦岩、権現杉、阿弥陀堂など
終わりに
今回は『日本書紀』に登場する女神・八女津媛神について紹介しました。
美人で子だくさんな女王だったようですが、果たしてどのような生涯を送ったのか、その生涯はいまだ謎に包まれています。
近くを訪れる機会に恵まれたら、ぜひ八女津媛神社にも参拝したいですね。