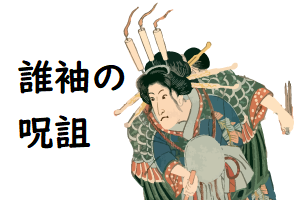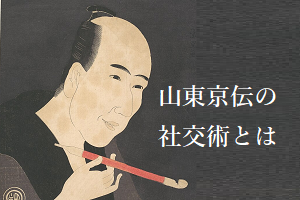文禄4年(1595年)7月15日、かつて豊臣秀吉の後継者と目されていた豊臣秀次(とよとみ ひでつぐ。羽柴秀次)が切腹しました。
一説には、罪なき人を面白半分に斬ったり撃ったりするなど、殺生関白(せっしょうかんぱく。摂政関白のもじり)と恐れられたことなどが一因と言われています。
他にも正親町天皇の崩御に際して喪に服さなかったり、比叡山の禁を犯したり……しかしそうした悪行三昧は、いずれも江戸時代以降の創作であり、秀次がそのような蛮行に及んだ確証は残されていません。
特に落度もなかったのであれば、なぜ秀次は死ななければならなかったのでしょうか。今回はそんな秀次事件について紹介したいと思います。
秀次、関白となる

豊臣秀次は永禄11年(1568年)、弥助(やすけ。のち三好吉房)と智(とも。秀吉の姉)の間に誕生しました。要するに秀吉の甥っ子です。
叔父・秀吉の立身出世に伴い、その一門衆として徐々に地位も向上していきますが、その運命が大きく変わったのは天正19年(1591年)でした。
8月に秀吉の嫡男である鶴松(つるまつ)が、わずか3歳で病死してしまったのです。
この時点で秀吉は55歳、当時の感覚では棺桶に片足を突っ込んでいてもおかしくない年齢でした。
元から子宝に恵まれない秀吉が、晩年になってようやく授かった我が子を喪った悲しみは、想像を絶するものでしょう。
しかし嘆いてばかりでは始まりません。同年12月、秀吉は秀次を養子として後継者に指名。関白の座を譲り、聚楽第へ住まわせたのでした。
関白とは言っても、始めは秀吉のお飾りでしかなかったでしょう。しかし年が明けて天正20年(1592年。文禄元年)になると、秀吉は朝鮮出兵(文禄の役)のために肥前名護屋城へ移住。中央政治の実権は次第に秀次に移行していきます。
このまま関白として実績を積んでいけば、名実ともに秀吉の後継者として天下に号令できたかも知れません。
しかし文禄2年(1593年)、再び秀次の運命が急展開を迎えることに。8月になって、秀吉にまさかの嫡男が誕生したのです。
拾(秀頼)の誕生で暗雲ただよう

拾(ひろい。のち豊臣秀頼)と名づけられたその子を、秀吉が溺愛したのは言うまでもないでしょう。
こうなると秀吉としては、自分の後継者を秀次よりも拾にしたいのが人情というもの。とは言え、さすがに関白≒後継者をコロコロ変える訳にもいきません。
そこで9月になって、秀吉は秀次を呼び出し、こんな提案を持ちかけました。
「日本を五つに分割し、うち四つをそなたに、残り一つを拾に分けてやってはもらえまいか」
「……」
加えて10月に入ると、秀次が湯治に出かけて不在のうちに、秀次の娘と拾の婚約を決定してしまいます。
あくまで秀次は拾が元服するまでの「中継ぎ」に過ぎないとアピールされたようなもので、秀次は「いつ粛清されるのか」と不安を募らせたことでしょう。
年が明けて文禄3年(1594年)。新年早々に秀吉は拾に大坂城を譲り、自身は築城中の伏見城へ移りました。いよいよ「拾こそが次の天下人である」と露骨なアピールが始まります。
とは言え、秀吉にしても万一に備え、拾の後見人となるかも知れない秀次との関係は円満に保っておきたいところです。
そこで同月中に秀次を招いて能を所望し、その返礼として2月に自身も秀次に能を披露しました。
ひとまず両者の関係は小康状態を取り戻したようです。が、これは嵐の前の静けさに過ぎませんでした。
出家させられ、切腹へ
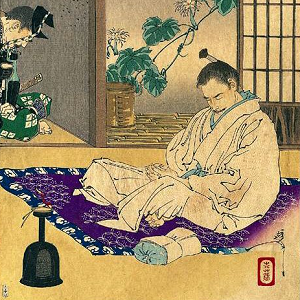
しばらく時が流れて文禄4年(1595年)。7月に入ると、秀次が謀叛を企んでいるという風聞が流れます。
「何をバカな……しかし、疑われてしまった以上は致し方あるまい」
潔白を証明するため、秀次は7月3日、秀吉に決して謀叛を起こさないとの誓紙を提出しました。
「やれやれ。これで少しは信用してもらえようか……」
と思ったら甘かった。たった5日後の7月8日、再び秀次が謀叛を企んでいるという風聞が流されたのです。
「何ゆえここまで立て続けに疑われねばならんのじゃ……」
秀次は急ぎ伏見へ出頭します。もちろん軍備の支度などはととのえず、ほぼ丸腰で潔白を主張したことでしょう。
しかし秀吉は面会を拒否。秀次の言い分など一切聞かず、出家して高野山へ下るよう命じられてしまいました。
関白から一転出家とは……あまりの理不尽に憤ったことでしょうが、秀吉が秀次の粛清ありきでいる以上はどうしようもありません。
まさか本当に謀叛を起こす訳にもいかないし、この場で逆らえば命もなかったことでしょう。秀次は泣く泣く出家し、7月10日に高野山へ入りました。
7月12日には秀次の幽閉が命じられ、7月13日には熊谷直之(くまがい なおゆき)や白江成定(しらえ なりさだ)が切腹。ほかにも有力家臣らが次々と失脚し、秀次は孤立無援と追い込まれてしまいます。
そして7月15日、福島正則(ふくしままさのり)らが軍勢を率いて秀次に賜死(しし。死を賜る=主君から自害を命じられること)の命を伝えました。寺院の僧侶たちは抗議しますが、福島の恫喝によって秀次は切腹を受け入れたのです。
遺族たちまで皆殺しに

磯かげの 松のあらしや 友ちどり いきてなくねの すみにしの浦
【歌意】磯辺で思わぬ嵐に見舞われたが、同じ境遇にある千鳥の啼き声は、何と澄み切ったことだろう。
月花を 心のままに 見尽くしぬ なにか浮き世に 思ひ残さむ【歌意】花鳥風月を思う存分に楽しんできた。これ以上、現世に何の思い残しがあるだろうか。
この歌は、秀次の辞世と伝わっています。理不尽極まる切腹を前にしながら、泰然と死を受け入れたのでしょうか。享年28歳。
秀次の首級は伏見へ運ばれ、秀吉は7月16日に検分しました。しかし秀吉は気が済まなかったようで、8月2日には京都・三条河原で秀次の遺族ら(男児4名、女児や妻妾。侍女や乳母など)39名が斬首したそうです。
中には秀次に嫁いで(嫁がされて)間もない娘もいましたが、そんな事情は一切考慮されません。無情にも処刑は執行され、そればかりか彼女たちの遺体をひとまとめに埋め、その上に秀次の首級を収めた石櫃が置かれました。
その後も多くの連座者を出し、秀次と何かしらの関係を持っていた者は片っ端から咎められたと言います。どれだけ憎かったのでしょうね。
終わりに

今回は秀吉の甥であった豊臣秀次がたどった非業の末路について、駆け足でたどって来ました。
本当に秀次が謀叛を企んでいた可能性がないとは言えないものの、どう見ても秀吉による言いがかりだったと見るのが自然でしょう。
かくして秀吉の望み通りに拾(秀頼)が後継者となったのですが、今回の事件を通して多くの大名たちから恨みを買うことになりました。
合わせて成人後の秀頼を支える一門を喪ったことも、豊臣政権の寿命を縮めた一因と言えるでしょう。
※参考文献:
- 小和田哲男『豊臣秀次 「殺生関白」の悲劇』PHP研究所、2002年3月