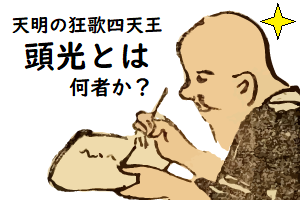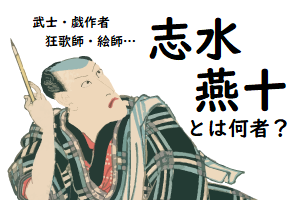NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」が新章に突入し、世の文化人らは狂歌の魅力に目覚め出しました。
我らが蔦屋重三郎(横浜流星)も例外ではなく、そこへ大田南畝(桐谷健太)が登場します。
狂歌界のスターとなった大田南畝(蜀山人)は多くの門人を輩出し、やがて天明年間(1781~1789年)のお江戸を牽引する存在となりました。
今回はそんな一人である頭光(つむりの ひかる)こと岸文笑(きし ぶんしょう)を紹介したいと思います。果たして彼は、どのような人物だったのでしょうか。
浮世絵師から狂歌師へ
岸文笑は宝暦4年(1754年)、但馬豊岡藩(京極家)に仕える家に生まれました。
実名は岸誠之(まさゆき)、通称を宇右衛門(うゑもん)。日本橋亀井町(東京都中央区日本橋小伝馬町)で町代(町役人)を務めます。
十代にして絵を志し、明和年間(1764〜1772年)に浮世絵師の一筆斎文調(いっぴつさい ぶんちょう)に弟子入りしました。
黄表紙の挿絵などを手がけ、天明年間(1781〜1789年)まで絵筆を奮います。
【岸文笑の主な作品】
- 黄表紙『往古模様亀山染』
- 紙本着色双幅「市川海老蔵と市川八百蔵」など
やがて狂歌を嗜むようになり、大田南畝の門人となりました。
狂歌師として桑楊庵(そうようあん)•頭光(つむりの ひかる)•二世巴人亭(にせいはじんてい)など、様々な号を使い分けています。
頭光とは大酒が過ぎて頭が禿げてしまったことに由来するとか。男性にとって、ハゲはセンシティブなテーマですが、なかなか度量の大きな人物だったのでしょう。
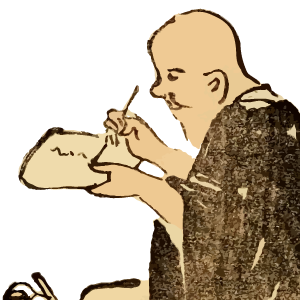
そんな頭光は天明狂歌四天王の一人に数えられます。
【天明の狂歌四天王】
- 鹿津部真顔(しかつべの まがお)
- 頭光
- 馬場金埒(ばばの きんらち)
- 宿屋飯盛(やどやの めしもり)
互いに切磋琢磨し、お江戸の狂歌界を大いに盛り上げたのでした。
また伯楽連(はくらくれん)と呼ばれる狂歌サークルを主催します。伯楽とは牛馬の目利き人を指し、転じて次世代の俊英を見出す自負を込めて名付けたのかも知れません。
自身の門人には浅草干則(あさくさの ほしのり。浅草海苔のパロディ、二世桑楊庵)や浅草庵市人(あさくさあん いちんど)らがいます。
狂歌集も出しており、個性豊かな作品を世に送り出しました。
- 『狂歌才蔵集(きょうかさいぞうしゅう)』/天明7年(1787年)
- 『絵本譬喩節(えほん たとえのふし)』/天明9年(1789年)
- 『圃老巷説菟道園(ほろうこうせつ うじのその)』/寛政4年(1792年)
- 『狂歌桑之弓(きょうかくわのゆみ)』/寛政4年(1792年)
- 『狂歌太郎殿犬百首(きょうか たろうどの いぬひゃくしゅ)』/寛政4年(1792年)など
しかし寛政8年(1796年)4月12日に43歳で世を去ってしまいました。
墓所は瑞泰寺(東京都文京区駒込)にあり、その法名を恕真斎徳誉素光居士(じょしんさい とくよそこうこじ)と号しています。
終わりに

ほとゝぎす 自由自在に 聞く里は 酒屋へ三里 豆腐屋へ二里
【歌意】ここでは、ほととぎすの鳴き声がいつでも聞けて風流なことだ。しかし酒屋へ三里(約12キロ)、豆腐屋へは二里(約8キロ)も行かねばならない。≒花より団子、ホトトギスより酒と肴(豆腐)の方が大事だ。
今回は大田南畝の門人であり、天明狂歌四天王の一人として活躍した頭光こと岸文笑について、その生涯を駆け足でたどってきました。
NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」にはまだキャスティング情報が出ていないものの、天明狂歌四天王が一堂に会する場面がきっと拝めるはずです。
果たして誰が配役されるのか、楽しみにしています!
※参考文献:
- 吉田漱『浮世絵の見方事典』北辰堂、1987年7月
- 日本浮世絵協会 編『原色 浮世絵大百科事典 第二巻』大修館書店、1982年8月