時は戦国乱世も終焉を迎えつつあった慶長20年(1615年)5月。
徳川(とくがわ)家の率いる江戸幕府が豊臣(とよとみ)家を滅ぼすための最終決戦、後世にいう「大坂夏の陣」が幕を開けようとしていました。
人質だった幼少期から数々の苦労を積み重ね、ついにここまでやって来た……徳川家康(いえやす)にとっては天下獲りの総仕上げとも言える晴れ舞台ですが、ここでちょっとしたアクシデントが起きます。

忠義とは何か、奉公とは何か……今回はその現場に立ち会った大久保彦左衛門(おおくぼ ひこざゑもん。忠教)のエピソードを紹介したいと思います。
並みいる譜代を差し置いて、新参者の旗奉行
大久保彦左衛門と言えば三河武士を絵に描いたような頑固者で、徳川家七代に仕えた譜代の忠臣ながら偏k……もとい世渡りが下手なため、歴戦と武勲の割に不遇をかこっていました。
大坂の陣では槍足軽の部隊を率いて家康の身辺を警護する槍奉行を拝命しましたが、その上位の旗奉行は、大久保一族の政敵(※)である本多上野介(ほんだ こうづけのすけ。正純)が依怙贔屓で抜擢した保坂金右衛門(ほさか きんゑもん)と庄田三太夫(しょうだ さんだゆう。安信)。
保坂金右衛門はもともと甲斐国のあぶれ者(武田の残党?)で武芸はからっきし、庄田三太夫はどこで拾った馬の骨だか(丹波国出身とも)。こちらも家中に武名が聞こえたものではなく、いずれも徳川家が江戸に入ってからの新参者です。
「……ま、ヤツらの親玉からして帰り新参じゃからのぅ……」
帰り新参とは一度主君の元を去った者が再び出戻ってくることで、ここでは本多上野介の父・本多佐渡守(ほんだ さどのかみ。正信)を指します。

彼はかつて家康を裏切って一向一揆に味方し、その敗亡後に放浪していたところを見るに見かねた彦左衛門の長兄・大久保忠世(ただよ。七郎右衛門)のとりなしで徳川家に帰参、親子ともども面倒を見てもらったと言います。
しかし、世が移り変わると次第に立場は逆転。政敵となった忠世の嫡男・大久保忠隣(ただちか)を謀略で陥れて改易(かいえき。領地没収)に追い込み、徳川幕府の中枢に居座ったのでした。
「主君に弓を引いた帰り新参が恩義を忘れて栄華を極め、忠義一筋に奉公して参った譜代の侍は冷や飯食い……ふん、世の中そんなものかも知れんな」
大きく溜息をついた彦左衛門と轡(くつわ)を並べるのは、同じく槍奉行で武蔵国(現:埼玉県および東京都)の住人・若林和泉守(わかばやし いずみのかみ。直則)。
「まぁまぁ大久保殿……古来『至誠通天(しせいつうてん。誠の心は天に通じる)』と申しますゆえ、我らが懸命のご奉公、お天道様は見てござろうよ」
「で、あればよいがの」
彦左衛門はぼやきながらも目線の先に、家康の馬印(うまじるし)が揺れるのをとらえていました。
後退する家康の馬印
「なに……本多内記(ないき。忠朝)が、討死とな……!」
「は!毛利豊前(もうり ぶぜん。勝永)の軍勢へ単騎(ただいっき)にて斬り込まれ、立派なご最期を遂げられましてございまする!」

その頃、家康の本陣では俄かに動揺が走っていました。
徳川方は総勢およそ15~16万に対し、豊臣方は総勢およそ5~6万。
ほぼ3倍の兵力差で圧倒的勝利が見込まれていたため詰めが甘く、予想外の激しい抵抗に被害が続出していたのです。
豊臣方としてみれば勝機を失ってしまった以上は死んで名を残すよりなく、文字通り死力を振り絞って勇戦したため、勝利に命を惜しむ徳川方を徐々に押しつつありました。
「敵襲ーっ!真田(さなだ。信繁、真田幸村)が突っ込んで来るぞーっ!」
「なに、真田じゃと!?」
真田と言えば、これまで親子二代で徳川家を翻弄し続けた難敵中の難敵。それが最期の力を振り絞り、家康ただ一人に狙いを定めて突撃してくると言うのです。
「ここは危のうございます!どうか、陣をお下げ下され!」
「うむ……誰か、馬を曳け!」
「は!」
かくして本陣を下げた家康に従って、総大将の居場所を示す馬印も移動しました。しかし馬印につき従うべき旗奉行の保坂・庄田両名は、前方の戦況ばかり気になって家康の馬印が動いたことに気づきません。

「……連中、どうも気づいていませんな。教えてやった方がよいのでは?」
若林和泉守が彦左衛門に耳打ちしますが、彦左衛門は涼しい顔で答えます。
「いや、大御所様(家康)から見込まれて御旗を預かるほどの人物であろうから、格下の槍奉行ごときがお教えするまでもあるまい」
「しかし……そうは言っても大御所様の御身に何かあったら……」
「ここから陣を下げると言えば、おおかた天王寺方面。地形や軍勢の配置などを考えて、大御所様の安全は確保されていよう。仮にも旗奉行を拝命するほどの方々であろうから、そのくらいの事は心得ておろうよ……」
「まったく(保坂・庄田がそんな心得のないことを察していように)、お人が悪い……」
「ま、先ほど連中が申した通り『槍は旗につき、旗は馬印につく』もの。我らはあくまでも槍奉行の務めをまっとうするべく、連中に従ってやろうではないか。万が一、旗が崩れるようなことがあれば、その時はそれがしと貴殿で立派に旗を立て、大御所様の元へ馳せ参じようぞ」
「……御意」
若林和泉守が苦笑していると、案の定と言うべきか、金右衛門が泣きそうな顔で駆け寄って来るのでした。
家康の馬印はどこに?
「大久保殿~っ!」
家康の馬印を見失ってしまった保坂金右衛門は、彦左衛門と若林和泉守に泣きついてきました。
(……本当に教えぬおつもりか?)
(無論じゃ)
互いに目配せを交わしてから、彦左衛門は自分の裾にすがりつく保坂金右衛門を軽く蹴飛ばします。
「何じゃ金の字、見苦しい……その方、よもや大御所様の馬印を見失った、などとは申すまいな?」
「そのよもや、よもやよもやにございまする~っ!」
文字通り泣き出しそうになっている金右衛門をもう少し強く蹴飛ばして、彦左衛門は怒鳴りつけます。
「このたわけ!その方、先ほど我らに宣(のたも)うたな……槍は旗につけ、旗は馬印につく、と……」

「……はい……」
「ならば探せ!万に一つ、大御所様の身に何かあってみろ、その薄汚い素っ首の百や二百では相すまぬぞ!」
「ひいっ……!大久保殿、大御所様はどこに……」
「(おおかた察してはいるが)知るか!槍奉行は旗につくのが務め、旗奉行が馬印の場所を知らないで、いったい何を知っていると申すのか!」
「そんな殺生な……どうか、どうか後生にございます。大御所様の馬印は何方(いずかた)へ……」
あんまり哀れに思ってか、若林和泉守が「彦左殿、物知らずをいじめるのもその位になされ」とたしなめます。
「……和泉殿が左様に申されるなら……まぁよい。金の字よ、大御所様は天王寺の方へ陣を移されたゆえ、あそこに見える茶臼山を左手に見ながら旗を進めよ」
「忝(かたじけな)い、忝い……!」
金右衛門は慌てふためきながら自分の軍勢を立て直し、天王寺方面へと進軍。
槍奉行である彦左衛門たちは、後から追い立てるようについて行きます……が。少し進んだところで、又しても保坂金右衛門が泣きついてきました。
「大久保殿~っ!」
「何じゃ今度は!」
「敵が!敵がぁ~……っ!」
見れば茶臼山に、豊臣方の旗が無数ひるがえっていました。保坂・庄田の率いる両軍に動揺が広がり、その旗がしきりに乱れています。
「たわけ!戦さ場に敵がおって何がおかしい!それよりも旗を見苦しくひるがえすでない!大御所様の名誉を傷つけるつもりか!」
「だって、敵があんなにたくさん……」
「いいから旗を前に進めろ!よいか、御主君がおいでになる場所であれば、たとえ地獄の底であろうとつき従うのが家臣の務めぞ!」
「ひぇぇ……!」
「オラ、疾々(とっと)と旗を進めんかい!後がつかえておるんじゃ、あんまりモタモタしておると、そのケツを槍で突き刺すぞ!」
とまぁ、そんな具合に旗奉行の両軍を後ろから急き立て急き立て連れていくうち、ようやく茶臼山の向こうに家康の馬印が立っているのを発見。金右衛門らは九死に一生を得た思いだったことでしょう。
旗を乱すな!グダグダな行軍
「あぁ、大御所様の馬印。ご無事みたいでよかったぁ……」
すっかり安心しきった様子の保坂金右衛門・庄田三太夫の目を覚ますかのごとく、天王寺の方面から鉄砲の音が響き、どうやら戦闘が始まったようです。
「すわっ。いよいよ始まった!」

慌てふためく金右衛門らでしたが、何の考えもなく軍勢を田んぼの中に進ませてしまい、思うように前進できずにいました。
「えぇい、足手まといじゃ。先に参るぞ!」
彦左衛門と若林和泉守が槍を旗より先に進めたところ、この期に及んでも金右衛門は「槍は旗に従うものだ」と抗議してきます。
「たわけ!いざ合戦に臨んで、その方は機を何に使おうと言うのじゃ。敵を叩くのは槍の仕事ぞ、道具の使い方も満足に知らんなら、恥をかかぬよう黙っておれ!」
「……ぐぬぬ……」
返す言葉もなく引き下がった金右衛門でしたが、それでも「大御所様の前で格下の槍奉行を出しゃばらせては格好がつかない」と面子にこだわって軍勢を無理やり押し出したので、又しても旗が乱れてしまいます。
「こらぁ!旗を乱すなと言っておろうが……っ!」
あきれ返った彦左衛門と若林和泉守は、これ以上の混乱を防ぐため、仕方なく旗奉行の後からついていくことにしました。
「さぁ進め!一刻も早く大御所様の元へ戻るのじゃ!」
ひたすら旗を押し進めていた金右衛門でしたが、いよいよ天王寺が近づいてくると最前線で戦っていた味方が豊臣方に押され、一目散にこちらへ逃げてきました。
「「うわぁ……っ!」」
あまりの勢いに保坂・庄田の両軍は翻弄されてしまいます。旗は散々に乱れた挙げ句放り出され、味方によって踏みにじられ、二人の姿も見えなくなってしまいました。
旗奉行の務めとは……
「者ども、こちらへ退避せよ!」
大混乱の中、彦左衛門は若林和泉守の軍勢とはぐれてしまったものの、急ぎ手勢をまとめて街道の脇によけます。
そこには家康が、馬印を持っていた小栗忠左衛門尉(おぐり ちゅうざゑもん。久次)と二人きりで立っていました。
日ごろあれだけたくさんいた側近たちはみんな逃げてしまったのか、あるいはこの機会に手柄を立てようと前線へ踊り出していったのか、誰もいなくなっています。
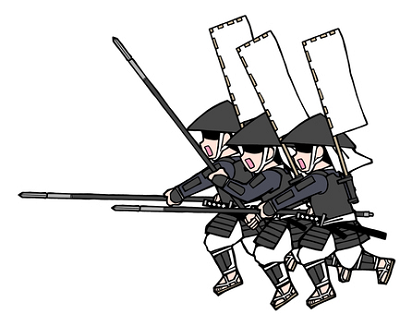
主君をおいて逃げるなどは論外として、手柄を立てようと言っても身分の低い者であればともかく、家中においてひとかどの重臣であればこういう時は主君の側近くに控えて護衛するのが務めであろうに……。
そんな心得もない者ばかりが取り立てられてきたことに、改めてがっかりさせられます。
しばらくして若林和泉守、だいぶ遅れて保坂と庄田の両名がバラバラと戻ってきました。
居たたまれなくなったのか両名は「(汚名を返上するため)これより前線へ出る!」と言うので彦左衛門は呆れ返って
「……お好きになされよ。我らは命じられたお道具の務めを果たす(=槍奉行の務めとして、家康を護衛する)まで」
と答えたところ、さすが勘の悪い金右衛門も気づいたようで「いかにもその通り。大御所様のご威容を保つため、旗をお守り致す」と、その場に留まることを理解したようです。
すると、保坂と一緒にいた庄田三太夫がきまり悪げに「敵が鉄砲を射かけてきたので、応戦のやむなきに至ったのだ」と、旗を乱すどころか投げ出してしまった言い訳をしてきました。
しかし、そんなことは混乱している戦さ場において誰にも確かめようがなく、後から何とでも言える……彦左衛門は両名に教えます。
「覚えておくがよい。旗奉行の役目はあくまで旗を保持し、軍勢の威容を示すことだ。目先の敵……もしあの場にそんなものがいたとしても……他の者、例えば槍に当たらせればよい。だからこそ、槍奉行たる我らが前に出たのじゃが……死んでも旗を立て続けることこそ、主君への忠義と心得よ」
「「……」」
こんな基本さえ判らぬ者を、旗奉行に命じられるとは……後から三々五々と戻って来る新参の家臣たちを前に、彦左衛門は大いに嘆息したのでした。
お前は旗だ!家康の剣幕に屈しない彦左衛門
さて。大坂の陣に勝利して積年の宿敵であった豊臣家を滅ぼした家康でしたが、とても不機嫌だったと言います。
勝って当然の戦さであったにも関わらず、旗が乱れたことで大恥をかいてしまったせいかも知れません。
「おのれ……旗を崩しおった失態は万死に値する!……旗奉行はお前か!」

ズラッと居並ぶ家臣たちの中から(恐らく昔から顔を見覚えているからであろう)彦左衛門を見つけて怒鳴りつけましたが、それだけ平素、顔も満足に覚えられないような浅い関係の者たちに取り巻かれていたのでしょう。
彦左衛門は槍奉行だったので、当然のごとく「畏れながら、それがしは槍にございました」と返答しました。しかし家康は顔を覚えている彦左衛門が旗奉行だったに違いないと思い込み、決めつけてかかります。
「お前は旗だったであろう!責任逃れをするでない!」
「いえ、それがしは槍についておりました」
「お前は旗である!」
「いいえ、それがしは槍についておりました」
「このわしが旗だと言っておるのだぞ!お前は絶対に旗奉行だったはずだ!」
いや。アンタの気まぐれで後から決めてくれるなよ……と思ってしまいそうです。しかし今や天下を我が手に収め、意にならぬことなどないとでも思っているのか家康は声を限りに怒鳴りつけます。
現代社会であれば、組織のトップからこうまで決めつけられてしまっては、いくら理不尽であっても「はい、やはりそれがしは旗にございました」と自分を枉(ま)げてしまいそうなものです。しかしそこは頑固者で知られた三河武士。
「いいいえ。どなたが何と仰せられましょうとも、それがしは此度、戦さの前に槍奉行を拝命してございます」
ぐぬぬ……今すぐこの場で叩っ斬ってやりたい衝動にも駆られましたが、辛うじて理性を保ちながら、家康は捨て鉢気味に叫びました。
「なら旗は誰だ!あぁ!?」
そこへ、彦左衛門の隣にいた小栗又一郎政信(おぐり またいちろうまさのぶ)が言い添えます。
「畏れながら、旗奉行につきましては、保坂金右衛門殿、庄田三太夫殿の御両名が拝命してございます」
小栗の言葉を聞いた家康、急にキツネにでもつままれたような顔になり、
「え……保坂?庄田?えーと、庄田、庄田、庄田……?」
恐らく、本気で旗奉行が誰だか覚えていなかったのでしょう。家康はポカンと譫言(うわごと)を繰り返しながら、のそのそと大広間を出て行ってしまいました。
崩れたはずの旗が立っていた?彦左衛門、かく語りき
家康が出て行ってしまうと、大広間の家臣たちは俄かにざわめき始めました。
「やはりお年なのじゃろうか、自分でお命じになった旗奉行をお忘れとは……」
「しかし何ということだ……大御所様の旗を崩してしまうとは……」
「保坂、庄田の両名は、厳罰を免れまいな……」
「……そもそも大御所様も、あんな連中に旗奉行をお命じになるとは……」
中にはその場にいなかった者でさえ、めいめい勝手に好き放題言っている連中に、彦左衛門はピシャリと言い放ちます。
「各々方……何か勘違いをなされておいでのようだが、旗は立っておりましたぞ」
え……?その言葉に、一同は怪訝な表情を隠せません。さっき家康は旗が崩れ、立っていなかったからこそ怒り狂っていたのですから。
「おい彦左、馬鹿を申すでない……旗は立っていなかった。なればこそ、大御所様がお怒りであったのだぞ!」

彦左衛門に食ってかかったのは松平右衛門尉正綱(まつだいら うゑもんのじょうまさつな)。家康に気に入られ、松平の分家に養子入りした権臣です。
「旗は立っていなかった……のぅ方々(かたがた)、そうであろう!」
松平殿が左様に仰せならば……とばかり、その場を見ていた者もそうでない者も、口をそろえて「我は見なかった」「それがしも見なんだ」などと同調します。
「それ見たことか。旗は崩れ、立っていなかったのだ。これは旗奉行の落ち度だ!」
「「「そうだそうだ!」」」
「……ふむ。皆がそう言うのだから、やはり旗は立っていなかった。そういうことに決したのだ」
多くの者が自分の権勢に同調する様子にドヤ顔な正綱に呆れながら、彦左衛門は言いました。
「……わかった」
「やっと解ったのか?この頑固オヤジめ!」
「そういうことではない」
「ん?どういう事だ?」
「……その方らが闇夜に旗を見なかったと言うなら、それがしは月夜に旗を見たのだ。その方らが月夜に旗を見なかったと言うなら、それがしは昼間に旗を見たのだ。よもやその方らは、現場を見もせで『旗は立っていなかった』と言っておるのではあるまいな?」
「「「???」」」
闇夜?月夜?昼間?……何のことだか、さっぱり意味が判らない……正綱はじめ一同は煙に巻かれた面持ちで、議論はそれきりとなったのでした。
「彦左殿……」
隣の又一郎は心配しましたが、それは間もなく的中することになります。
それでも旗は立っていた!天下人を唸らせた彦左衛門の強情さ
「大久保殿……大御所様より直々にご詮議の用これあるにつき、御前へ参られよ!」
それ見たことか、みんなの前で訳の判らんことを申されるから……又一郎の心配もよそに、彦左衛門は家康の元へ参上しました。
「……大久保彦左衛門、罷り越してございます」
「お前は……槍を持っておった者じゃな」
「は。左様にございまする」
次の瞬間、家康はいきり立って彦左衛門が手をついている畳のすぐそばを踏みつけ、声を限りに叫びます。
「お前はどうして、わしにつき従わなかった!」
老いたりとは言え、家康は「海道一の弓取り」と天下に恐れられた戦国大名。その気魄は匹夫ならば到底耐えうるものではなかったでしょうが、彦左衛門もまたその家康を支え続けた譜代の忠臣。毅然として答えます。
「畏れながら申し上げます。槍は旗に付き従うものにございますれば、旗の立っていた大和口の陣場におりました」
「その旗は、立っていない筈だ!」
「いえ、旗は立っておりました」
「皆も見なかったと言っておる。旗は立っていない!」
「いいえ。有象無象が百人千人束になって、いかほど声を大に何と申そうが、旗は立っておりました」
頭に血が上った家康は、怒りに震える左手で脇差を握りしめ、右手の杖でホコリが舞い上がるほど強く畳を突いて絶叫します。
「こ・の・わ・し・が!『見なかった』と言っておるのだ!断じて絶対に旗は立っておらなんだ!」
しかし彦左衛門、なおも怯まず
「いいいえ。どなたが何と仰せられようと、旗は大和口の陣場に立っておりました!」
家康は今にも卒倒せんばかりに怒りを漲らせながら、地鳴りのような声を絞り出します。

「弓矢八幡(※1)、稀有の天道に誓って(※2)、わしは一代の内に戦で逃げたことはない(※3)と言うのに、お前はわしが『逃げた』と言うのか……」
旗が立っている場所に大将がいなかったということは、すなわち陣場を捨てて逃げ出したことに外ならず、家康にとってはこの上ない屈辱でした。
(※1)八幡大菩薩。源氏の氏神であり、武士たちの守護神である八幡神。
(※2)けうのてんとう。太陽すなわち天照大御神(あまてらすおおみかみ)。天地神明にかけて、の意味。
(※3)元亀3年(1573年)12月22日、三方ヶ原の合戦で武田信玄(たけだ しんげん)公に撃ち破られて這々(ほうほう)のていで逃げ出したことは、この際ノーカウントとしているようです。
「……」
流石の彦左衛門もハッキリ「そうだ」とは言えず、ただ家康の目を睨み据えるだけでしたが、誰よりもすべて(自分が真田の猛攻に怯んで、後退してしまったこと)を解っている家康は、悔し紛れに続けます。
「……大久保は強情だ……みんなみんな強情だ……七郎右衛門(彦左衛門の長兄・忠世)も治右衛門(次兄・忠佐)も強情だったが、お前は兄弟一の強情者だ……相模(忠世の嫡男・忠隣)を引き立ててやった恩義もあろうに、お前は本当に強情なヤツだ……!」
その相模をいわれなき讒言によって改易し、大久保の嫡流を取り潰してくれやがったのはドコのボケ狸だ!……と彦左衛門も言いたかったところでしょうが、流石に堪えていると、本多上野介正純がやって来て、彦左衛門の腕をつかみます。
「立たれぃ!これ以上の屁理屈は許さぬ!」
「……しからば、これにて……」
「……(お前なんか嫌いだ!あっちへ行け……!)」
退出する彦左衛門の背を睨む家康の眼には、どこか寂しさとも悔しさともつかない感情が入り混じっているようでした。
旗の恥は、主君の恥……彦左衛門の愚痴
「あの頑固者の彦左衛門が、あろうことか大御所様にタテ突きおった……」
さて、家康にタテ突いたことに対する処分について協議されている間、謹慎していた彦左衛門の元に小栗又一郎がやって来ました。
「おぅ、又一殿か。よう来られた」
出迎えた彦左衛門は、今にも腹を切らんとばかりの白装束。流石の又一郎も驚きます。

「……彦左殿のことであるから、無論お考えもあるのだろうが、此度の一件は旗奉行の落ち度としておけば済む話を、何ゆえ左様に言立てなさるのか?」
「旗の恥は、主君の恥に外ならぬ!」
彦左衛門の話すところによれば、強弁の理由は以下の通りでした。
「わしは大御所様の代まで徳川家七代にお仕えした譜代の家臣として、主君の象徴である旗にキズをつける訳にはいかぬ。どれほど旗が乱れ、崩れようと『旗は逃げなかった、立っていた』と申し上げるのが務めであり、それでご機嫌を損ねて腹を切らされようが首を斬られようが、我が身可愛さに『旗が逃げた』とは口が裂けても言えぬ。いま大御所様の周りを取り巻いている連中は目先のご機嫌とりばかり考えて、徳川家の行く末のことなどまるで考えてはおらぬ。もはや大御所様も齢七十を過ぎて、最大の敵であった豊臣を滅ぼした今、崩れた旗の汚名を雪ぐ戦はあるまい。そこまで考え見通したならば、決して保坂や庄田なにがしの落ち度で済ませられる話ではないのだ」
古来、旗奉行は家中の名誉であると同時に、その失態は任じた主君の失態でもありました。だからこそ、滅多な者には任せることなく、信頼できる譜代の家臣から特に選抜したものです。
「……寂しいのぅ……」
深くため息をついた彦左衛門に、又一郎は黙ってうなづきます。
「大御所様ほどの御方であっても、歳をとれば御目が曇るか……顔も名前も覚えておらんような新参者が、わしら譜代の家臣よりもマシにお見えになろうとは……」
弱小だった頃は徳川を鼻で嗤っていた連中が、ひとたび家康が天下人となるや手のひらを返して媚びへつらい、そうした者ばかりが幅を利かせる一方で、苦楽を共にしてきた譜代の家臣は蔑ろにされる……彦左衛門の偏屈な性格も、そういう積み重ねの産物でした。
「……詮なき愚痴を、お聞かせ申した……」
「……いや。彦左殿のご真意、篤き忠義のほど、よう解り申した。かくなる上は堂々と御前に出て、思う丈を存分にお話し召されい。介錯(切腹の介助≒とどめの斬首)はそれがしが承ろう」
「お頼み申す。又一殿なら、安心してこの首をお任せできる」
ホッとしたように笑いながら、彦左衛門はさっそく白装束の上から裃(かみしも)を身につけた正装で、家康の元へと出発したのでした。
エピローグ
……で、彦左衛門が腹を切ったのかと言えばそんな事はなく、いざ登城してみると他の者たちは騒然として「大御所様にタテ突いて、さぞや気まずかろうに、よう出て来た」と称賛の嵐。
また彦左衛門の真意が伝わったのか、自分の不覚を恥じた家康も、少々気まずそうな感じだったそうです。
「やれ天下人々々々と、もったいつけて宣(のたま)うが、あなたにその天下を獲らしめたのは、いったい誰のいかなる働きか」
こと失態を演じた保坂、庄田の両名を旗奉行に推薦した本多上野介正純の仏頂面などは実に痛快で、これまで本多一族の謀略によって陥れられ続けた大久保家にとって、一矢報いた形になったでしょうか。
果たして慶長20年(1615年)7月、天下泰平の世が訪れたことを示すべく元和(げんな)と改元。戦国乱世の終結(元和偃武-げんなえんぶ)が宣言された翌年、すべてを成し遂げた家康は静かに世を去ったのでした。

その後も彦左衛門じいさんは24年も長生きして、自称「天下のご意見番」として活躍?するのですが、そのエピソードはまたの機会に。
※参考文献:
小林賢章 訳『三河物語(下) 将軍家と譜代大久保家』教育社、1980年1月




コメント