お出かけ前と おやすみ前に
家の戸締り 火の用心(都々逸)
私たちの暮らしと深く関係している鍵と錠前。
家や職場の戸締りや、金庫・物置・その他もろもろ……錠前に鍵を差し込んで、施錠/解錠するやりとりは、誰もが経験したことがあるはずです。
ところでこの鍵と錠前はいつからあるのでしょうか。
そんな疑問を解消するため、今回は鍵と錠前の歴史について紹介したいと思います。
最古の錠前は飛鳥時代?

日本で鍵と錠前が使われ始めたのは飛鳥時代(7世紀ごろ)と言われ、最古の錠前が野々上遺跡(大阪府羽曳野市)から出土しました。
海老が腰を曲げたような形をしていることから「海老錠」と呼ばれていますが、残念ながら真っ赤に錆びついて今では開閉できません。
今でも開閉できる最古の錠前は奈良時代(8世紀)のもので、東大寺の正倉院に納められています。
これらはいずれも大陸からの輸入品と考えられ、国産の鍵と錠前はあまり普及しませんでした。
戸締りと言えば、戸板と壁にはさむ心張棒(しんばりぼう)か門扉をつなぐ閂(かんぬき)が主流で、鍵と錠前が普及するのは江戸時代を待たねばなりません。
江戸時代の錠前

江戸時代に入ると錠前の絡繰(からくり)を造る職人が現れ、各地で京錠や土佐錠など地名を冠した錠前と鍵が造られるようになります。
ただし一般庶民の間にはまだまだ広まらず、家の戸締りは相変わらず心張棒という世界でした。
江戸時代の錠前は鍵を差し込んで回すと解錠できるウォード式が主流です。
当時はまだ複雑な鍵を造れず、合鍵やピッキングで容易に開けられてしまう欠点が悩みでした。
そこで錠前職人たちは知恵をめぐらし、鍵穴を複数造ったり(鍵を差し込む順番を間違えると開かない)、そもそも鍵穴を見つけにくくしたりなど工夫を凝らしたそうです。
近代~戦前の錠前

やがて明治時代に入ると、洋風建築や洋式ドアとセットで錠前も普及しました。
和式の引き戸から洋式のドアへ移り変わり、心張棒では戸締りができません。
※閂式の戸締りはその後も小型化しながら各所で散見されます。
大正3年(1914年)には洋式錠前の国産第1号「白玉錠」が誕生しました。
これは白磁のドアノブに鋳物の錠前を組み込んだもので、その洗練されたデザインが人気を呼んだことでしょう。
やがて昭和時代に入ると、輸入に頼っていたシリンダー錠の国産化が進み、より一般的なものとなりました。
しかし大東亜戦争が始まると金物メーカーは軍需産業へ転換を余儀なくされ、錠前文化の発展は足止めをくらいます。
戦後の錠前

敗戦後から高度成長期にかけて、円筒錠(シリンドリカルロック)が普及し、一般庶民の住まいにもドアが当たり前になっていきました。
この頃になると都市部では人口が密集し、それにともない犯罪も増えていきます。
防犯性能を高めるため、ドアの内側に錠箱を設け、こじ開けを防ぐサムターン式の錠前なども普及しました。
またドアの把手もノブだけでなく、レバー式ハンドルが普及。内装と調和したデザインを楽しめるようになっていきます。
これからの錠前

日本史上最長の元号である昭和も終わりにさしかかり、平成・令和の現代では、オートロックが採用されるなど鍵と錠前も大きく進化をとげました。
磁気カードやテンキー(暗証番号)を用いた電気錠、指紋による生体認証など、セキュリティ機能は格段に高まっています。
また昨今ではIoT(Internet of Things)による遠隔操作も可能となっており、外出先から自宅の施錠/解錠ができるなど、今後ますます便利になっていくことでしょう。
もしかしたら、ドア自身が通すべき相手かどうかをAIで判断する……なんて未来が来るかも知れませんね。
※参考文献:
- 赤松征夫『鍵と錠の世界』彰国社、1995年5月



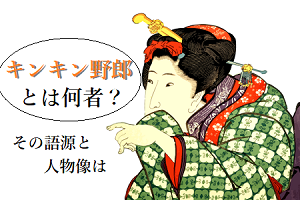
コメント