日本で一番漢字の多い名字(※)とされる勘解由小路(かでのこうじ)さん(※ちなみにトップタイは左衛門三郎さん)。
その由来は平安京の勘解由小路、現代の下立売通(しもたちうりどおり)に相当する通りと言われています。
(※異説あり。下記参照)

きっとこの辺りに屋敷でもあったのでしょうが、勘解由という変わったネーミングは、勘解由使(かげゆし)という官職に由来するもの。
ところでこの勘解由使とは、いったいどんな職務を担当していたのでしょうか。今回はそれを調べて紹介したいと思います。
国司の業務引継ぎを監査
今は昔、律令国(現代なら都道府県のイメージ)を治めていた国司が任期を満了すると、後任者が業務の引き継ぎにやって来ます。
やれ年貢の未納はないか、官品の横領はないか、帳簿のごまかしはないか、未解決の訴訟はどうなっているか……などなど、立つ鳥跡を濁さぬよう、キチンと申し継ぎが済んだら、後任者が前任者に対して解由状(げゆじょう)という書類を発行したのです。
「お役目、ご苦労様でした。あなたがちゃんと職務をまっとうされたことをここに証します(意訳)」

解由は「とくる(の)よし」とも読み、要するに「職責を全うして任務を解かれたこと」を意味するもので、かくして解由状をもらった前任者は都にこれを持って帰るのですが、これがないと次のお役目をもらうことができません。
普通に仕事をやっていれば大抵は発行してもらえるのですが、中には諸般の不手際から解由状をもらえなかった者が、解由状を偽造することもあったのだとか。
そこで勘解由使が登場、和名で「とくるよしかんがふるのつかさ」と言うように、勘とは勘案すなわち前任者が持って来た解由状を他の書類や報告などと照合、監査するのが仕事でした。
ちなみに、前任者の放漫経営や不正などが原因で解由状が発行されなかった場合、後任者は代わりに不与解由状(ふよげゆじょう。解由を与えず)を発行します。
これは後任者がなぜ解由状を発行しなかったかという理由(前任者の不手際)と、それに対する前任者の弁明という双方の主張が記され、これを元に訴訟が起こるのですが、その審判も勘解由使が担当しました。
平安時代、桓武天皇が設置

勘解由使は平安時代初期の延暦16年(797年)ごろ、桓武天皇(かんむてんのう。第50代)が国司の引継ぎチェック体制を強化することで地方行政の改善(不正の防止やトラブルの早期解決化など)を目的に設置したと言います。
その後、平城天皇(へいぜいてんのう。第51代)が即位した大同元年(806年)に勘解由使は一度廃止され、国司の引継ぎは道単位(東海道、中山道、北陸道……など)で地方行政を監察する観察使(かんさつし)が担当しました。
しかし、観察使の裁量によって公平性を欠いた(※)のか、国司の交替時にトラブルが増加、天長元年(824年)に再び勘解由使が設置されます。
(※)前任者による不手際があれば、そのとばっちりをまともに受ける後任者の厳しい目よりも、どちらかと言えば他人事になりがちな観察使の目は、前任者によって甘くなりやすかったのかも知れません。
先ほど紹介した不与解由状のシステムはこの再設置時に導入されたもので、これによってお互いの争点を明らかにし、紛争解決の手掛かりとしたのでした。
終わりに
以上、勘解由使について調べてみましたが、こうした行政システムの歴史を見ると、よりよい社会を作っていこうとする先人たちの試行錯誤のプロセスが浮かび上がって、とても興味深く思います。
いつの時代にもトラブルは絶えず、その解決を目指す者もまた絶えず……いま身の回りで当たり前に適用されている社会システムも、その一つ一つに歴史が必ずありますから、興味を持ってみると楽しいですよ。
追記(令和6年4月5日)
以前、朝廷の官職である勘解由使(かげゆし)について紹介させて頂きました。
京都にある勘解由小路(かでのこうじ)はこの勘解由使に由来するのであろう……そんな説を紹介したのですが、実はそうではないとする異説もあると言います。
今回は読者の方から教えて頂いた説について紹介しましょう。
(以下、読みやすく要約しています)
勘解由小路は平安時代から「かでのこうじ」と呼ばれており、例えば藤原忠実の日記『殿暦』では「カテノ小路」、歴史物語『大鏡』でも「かてのこうち」と書かれています。
最初から勘解由使の庁舎がおかれていたことが地名の由来であるなら、読みは「かげゆのこうじ」とするのが自然ではないでしょうか。
この「かでのこうじ」という読みは「神解小路(かむでのこうじ)」から来ていると言い、藤原実資『小右記』などにも書かれています。
呼び習わしていく内に「む(ん)」が抜け落ちて「かでのこうじ」となったのでしょう。
この神解(かむで、かんで)とは「落雷」を意味しており、『中右記』などでは「雷解小路」、『二中記』などには「神鳴小路」と表記されています。
恐らく大きな(死者が出るレベルの)落雷事故でもあったのでしょう。
しかし雷では縁起が悪いから、と神の字を勘に改めて「勘解小路」。勘解とくれば勘解由であろう……そんな経緯により、いつしかこの小路を勘解由小路と書いて「かでのこうじ」と呼ぶようになりました。
……という説でした。
厳密な記録がないため、仮説の域を出ませんが、なるほど確かにありそうですね。
情報提供、ありがとうございます。
まだまだ知らない事や新事実などがたくさんあると思うので、皆さんからの情報やリクエストなど、今後も募集中です。
※参考文献:
- 森田悌 訳『日本後紀 中 全現代語訳』講談社学術文庫、2006年11月


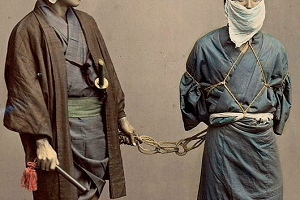

コメント