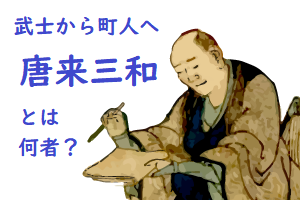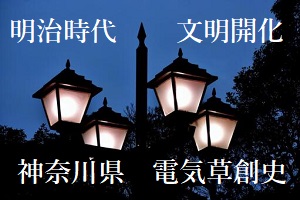唐来三和/山口森広
とうらい・さんな/やまぐち・しげひろユーモアのセンスにたけた、江戸の戯作者・狂歌師
もともとは武士の出身であったが、天明期に訳あって町人となる。
絵師、狂歌師、戯作者たちを集めた大規模な宴席で、蔦重(横浜流星)と出会う。代表作に『莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき)』、題名が上から読んでも下から読んでも同じ、回文の傑作がある。
やがて松平定信の時代に変わると、自ら発表した作品が政治批判をしたとされ絶版処分を受けてしまう。※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。
生まれ育った吉原遊廓を出て日本橋の通油町(とおりあぶらちょう)へ進出し、書肆(本屋)として地位を確立していく蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)。
新たな舞台でも様々な出会いがあり、さらなる飛躍のキッカケとなります。
今回は蔦重を触発する一人となった唐来三和(とうらい さんな/さんわ)を紹介。果たして彼はどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。
武士から町人へ

唐来三和は延享元年(1744年)に誕生しました。蔦重より6歳年長に当たります。
苗字は加藤、元は高家何某(※)の家臣であったのが訳あって武士を辞め、町人となりました。
(※)高家(こうけ)とは古くからの名門(例えば元戦国大名など)で、幕府のしきたりや作法をレクチャーするなど顧問的な存在です。
ともあれ町人となった唐来三和は江戸本所松井町にある妓楼・和泉屋へ婿入りし、和泉屋源蔵(いずみや げんぞう)の屋号を称しました。
唐来三和(又は参和)とは狂歌師としてのペンネーム(狂号)で、他にも質草少々(しちぐさ しょうしょう)・唐来山人(とうらいさんじん)など使い分けています。
※以下「唐来三和」で統一しましょう。
松平定信から絶版処分を受ける
唐来三和は蜀山人(しょくさんじん。大田南畝)に弟子入りし、多くの狂歌を詠みました。
また狂歌だけでなく戯作者としても活躍しており、以下にその作品を紹介します。
天明3年(1783年)
- 洒落本『三教色(さんきょうしき)』
- 狂歌集『狂文宝合記(きょうぶんたからあわせのき)』
天明4年(1784年)
- 黄表紙『大千世界牆の外(だいせんせかい かきねのそと)』
- 狂歌集『老莱子(ろうらいし)』
- 狂歌集『手拭合(たなぐいあわせ)』
天明5年(1785年)
- 洒落本『和唐珍解(わとうちんかい)』
- 黄表紙『莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき)』
- 黄表紙『頼光邪魔入(らいこう じゃまいり)』
- 狂歌集『徳和歌後万載集(とくわか ごまんざいしゅう)』
- 狂歌集『十才子名月詩集(じっさいし めいげつししゅう)』
天明6年(1786年)
- 黄表紙『通町御江戸鼻筋(とおりちょう おえどのはなすじ)』
- 狂歌集『吾妻曲狂歌文庫(あづまぶり きょうかぶんこ)』
寛政元年(1789年)
- 黄表紙『冠言葉七目十二支記(かんむりことば ななつめのえとき)』
- 黄表紙『天下一面鏡梅鉢(てんかいちめんかがみのうめばち)』
寛政5年(1793年)
- 黄表紙『再会親子銭独楽(めぐりあう おやこのぜにこま)』
寛政7年(1795年)
- 黄表紙『善悪邪正大勘定(ぜんあく じゃしょう おおかんじょう)』
実に勢力的な文筆活動を展開した唐来三和。しかし黄表紙『天下一面鏡梅鉢』が、松平定信の主導する「寛政の改革」を批判したとして、絶版処分を受けてしまいました。
しかしその後も復活し、精力的に文筆活動を続けます。
そして文化7年(1810年)1月25日に67歳で世を去ったのでした。
終わりに

今回は狂歌師や戯作者として活躍した唐来三和について、その生涯をたどってきました。
果たして大河ドラマべらぼうでは、山口森広がどのように演じ、魅せてくれるのでしょうか。
今後ますます多彩な人物が登場するので、楽しみにしています!
※参考文献:
- 徳田武 校注『近世物之本江戸作者部類』岩波書店、2014年6月
- 日本古典文学大辞典編集員会『日本古典文学大辞典 第4巻』岩波書店、1984年7月